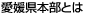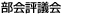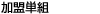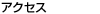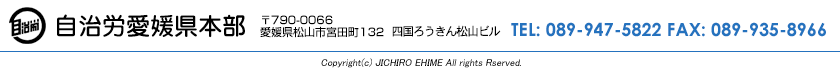2012年度
「子ども子育て新システム」における財源の取り扱い要請(2011.12.21、26)
- 県本部は、すべての子どもに質の高い保育サ-ビスを提供するために、制度・財源の一元化による効率的運営と確実かつ安定的な財源の確保を実現することをめざして、「子ども子育て新システム」における公立施設財源の取り扱いに関する要請を、県本部保育部部会を中心に、12月21日に県市長会長及び県町村会長へ、26日に県知事に行った。
子ども子育て新システムは、政府において、子ども子育てに関する財源・制度の一元化による切れ目のないサービス提供体制を構築することを目的とした「子ども子育て新システム」の創設のための成案のとりまとめに向けた検討が行われています。
この法案提出に向けた制度設計にあたって自治労は、①すべての子どもの最善の利益を確保するため、制度・財源の一元化による効率的給付体系を構築し、住民にとって利用しやすい仕組みとすること、②実施主体である市区町村が安定的な財源を確保し、子どもに対し確実にサ-ビスが提供されることが必要であると考えています。
しかし、現行制度では、保育所の設置主体により、保育保障の水準に格差が発生する可能性があるとともに、不交付団体や小規模市町村など、市町村によっては財源を十分かつ確実に確保できないため、市町村間に実施水準の格差が発生する可能性があります。
こうした制度の矛盾を、県市長会長、県町村会長、県子育て支援課長と協議する中で、「自治労の趣旨や考えは十分理解できた。県市長会や県町村会にも自治労の要望を伝え協議していきたい。また、県子育て支援課は、子どもに対しての保育が疎かになってはいけないと認識している。この問題を議論する国のPTに愛媛県もメンバーに入っており、国にも積極的に申し入れを行うともに知事にも自治労から要請があったことをキチンと伝えていく」との見解を示した。
県本部は、今後も「子ども・子育て新システム」における「こども園給付」創設にあたり、保育所の給付財源の取り扱いを公立・私立共通の「子ども・子育て包括交付金(仮称)」とするため全力で取り組みを進めていく。



伊方原発停止・廃炉にむけて(2011.12.24)
-
12月24日9時30分から愛媛共済会館で、「伊方原発停止・廃炉」愛媛・大分県共闘会議が結成されました。愛媛からは社民党村上県連代表、平和運動センター松本議長が代表に、事務局長に石川稔県会議員が選出されました。大分市は伊方原発から50キロ圏内にあり、福島第一原発事故のような事が起こると、佐田岬半島の多くの住民の受け入れや被害が予想されるため県民は危機感を持っています。共闘会議は伊方原発の廃炉を目差し学習・講演、集会等の取組と、「伊方原発をとめる会」を支援していきます。
当日、社民党の福島瑞穂党首が中村知事と会談し、伊方原発の1号・2号炉の廃炉、3号炉の再稼働を認めないでほしいと要請。共闘会議結成後、記念講演会を行い120名が参加、市駅前で街頭演説を行い「交付金は来なくても放射能は振ってくる」「子どもの命や自然を守るため愛媛から変えてほしい」と訴えました。



市町会長交渉(2011.12.06)
-
2011年12月6日(火)16時から愛媛県町村会長の白石勝也(松前町長)と「自治体職員の賃金労働条件の改善」について交渉を行いました。
出席者は、県本部から若宮執行委員長・井川書記長・山内(町村評議長)・木口(町村評事務局長)の4名で参加致し愛媛県町村の方は、会長の白石勝也(松前町長)事務局は、渡部(町村会事務局長)・柏原(総務課長)・向井(課長補佐)の4名が対応して頂きました。
冒頭、白石勝也町村会長は、今回の人事院・人事委員勧告は、東北の震災があっただけに致し方ない。市や町は民間と比べると給与水準が高いというのも現実にはある。税と社会保障制度と定年延長の事もある事から、どこかで負担を抑えていかなくてはならないのでは?難しい問題ではあるが。しかし、交付税に関しては、今回の震災があるとは言え、交付税を減らしてと言う考えにはならないと思うが、前年並みに維持できそうな感じではないかと思う。
現在、全町では、自動車贈与税・取得税が廃止という事で議論されているが、全町としては反対の意向を示している。逆に、代償の税がある訳でもないのだから。
子ども手当にしても結局は全額が国の負担と言う状況だったが、所得制限等で結局地方の負担が増えてきている事も事実である。との挨拶で、要求書の内容に入った。主な内容として以下の事が協議されました。
1.市町村合併に伴う賃金調整について
職員全体の志気にも係わる事から町長の方には言っておきます。2.2011年の人事院・人事委員勧告について
冒頭述べたように今回は、震災もあり仕方ないことでもある。3.7級制導入による5級到達に関して
伊方については、今年4月から6級制を導入しています。松野・鬼北については、未だ5級なので、同じ自治体の町の職員でもある事から、統一的な見解を申し入れして頂くよう町村会としても働きかけて頂きたい。12月16日には町長も集まるので話しはしておきます。
以上


部落解放共闘四国B交流学習(2011.11.26〜27)
- 歴史から闘いを学ぶ
- 部落解放共闘四国ブロック交流学習が11月26~27日に四国中央市土居町で行われ約50人が参加しました。
26日には土居町隣保館で「土居町の差別解消の歩み」「中学校での同和教育の取組と現状」「土居中事件」の報告等、差別の現実と同和教育潰しの闘いの報告がありました。
翌日は同和対策事業、明治の中頃、分教場で教育に携わり県下で初めて村会議員になった岩崎伊三郎の碑や明治36年から差別教育の撤廃、分教場廃止を訴へ続けた非戦論者安藤正楽碑、土居町人権宣言碑を尋ね、最後に暁雨館で安藤正楽の生き方に学ぶ講演を聞きました。
歴史に名を残す人はその時代には受け入れられなくても、功績は後の人が評価するのではないか、信念を持って行動することは、後に時代を変えると希望の持てる交流学習だった。
虐げられた時代には労働者・農民・解放運動が労・農・水同盟を結び「労働者の解放なくして部落解放なし」「部落解放なくして労働者の解放なし」と叫び行動を共にしたいた歴史がある。今はどうだろう、非正規職員が3割近く、生活保護世帯が戦後最多、自殺者が毎年3万人以上、高校・大学を出ても就職先がない、地震・津波・台風・原発、先の見えない社会の不安や不満が、一部の勢力になびいて行く危険があるのではないでしょうか。
自らが声をあげることによって、社会を変え、平和で誰もが安心して暮らせる社会を作れると思います。



地連書記会議総会・交流会開催(2011.11.25〜26)
-
11月25~26日松山市にぎたつ会館にて、自治労四国地連書記会議第7回総会・交流集会が開催され、2日間を通して4県本部19単組45人の参加を得た。
25日の総会では、池田地連書記会議議長、地元県本部として若宮愛媛県本部委員長、久知良全国書記会議副議長より挨拶を頂いた後、2011年度経過報告を受け、2012年度運動方針と2012-2013年度役員体制が可決された。
引き続き、四国地連書記交流集会が開催された。久知良全国書記会議副議長より『全国書記会議・協議会の取り組み』との基調提起を頂いた。これは、2013年6月には各県支部段階で統合する自治労共済と全労済において、2012年5月末には自治労側からの転籍者を選出すべき必要があることから、もう時間がないと言われている。自治労にはたらく書記を取り巻く統合問題について、説明や取り組み経過等が含めてなされた。
その後、現在58歳を迎えられ、35年以上自治労運動に関わってこられた横山書記より、『私と書記労働』と題し記念講演を受けた。『ストレスは人生のスパイスだ』『書記の仕事に誇りと責任を持とう』と言ったエールから、『誰かが底支えをして目配せをする。組合ではそれをするのは書記』『心は常に現場に。書記は事務屋になるな。…現場に入り、意見を聞くことの大切さ』『社会情勢に強くないと書記としても生き残れない。学習会作り・役員づくりは避けて通れない。書記自身も学ぶことが大切』等、書記の経験を元に、先輩より投げかけて頂く内容であった。
続いて、各県本部からこの一年間の取り組み報告があった。各県本部とも、書記同士の横のつながりを強める取り組みや学習を深める取り組みがなされた。
それから、2日間にわたる分散会へと移った。自治労にはたらく書記同士で集まる機会はそうないことから、それぞれが事前記入してきたアンケートを元に議論を深めた。ひとえに書記と言えど、単組で全てを網羅してはたらく、いわゆる一人書記もいれば、業務分担をしている書記もいる。かつ、県本部書記においては、全労済統合協議について他県状況を確認すべく、内容は多岐にわたっていたことが、翌26日の各分散会からの報告も伺えた。
26日の最後には、森議長より『書記は組合運動の土台。上は、その時の情勢・役員によって変わるが、土台がしっかりしていないとどうにもならない。誇りと書記の強い思いを持って頑張ろう』と最終集約を頂き、会は締めくくられた。
なお来年は、徳島県開催を予定している。毎年、地連内の四国各県で開催しているが、2巡目を終える予定。
★25日夜の交流会での各県本部紹介では、開催県本部である愛媛県本部内から参加した書記たちがAKB48に扮して、ナイロン袋等で作ったスカート衣装や練習をしてきた踊りを披露し、楽しく交流を深めた。



連合愛媛第21回定期大会開催される(2011.11.24)
- 自治労より、谷口副執行委員長が女性枠で新たに執行委員に選出される
- 11月24日、10時より松山市「ピィアフル松山」において、第21回連合愛媛定期大会が開催され、約150人(自治労代議員9人)が参加した。
冒頭、連合木原会長から「復興・再生に全力を尽くし、働くことを軸とする安心の実現に向けて、連合愛媛が掲げる7つの運動方針に添って全員で取り組みを強化しよう」との力強い挨拶を行った。また、来賓として出席した中村知事、野志松山市長は、「県政・市政の立場で連合愛媛と継続的な意見交換を行い、行政に反映できるよう今後も連携を深めていきたい」と挨拶を行った。
議事に入り、2011年度経過報告、2012・2013年度の運動方針(案)が提案され、質疑の後、代議員の満場一致により採択された。また、役員改選も併せて行われ、渡辺専従副事務局長の退任にともない、新しい専従副事務局長に電機連合の小寺悟さんが就任した。また、自治労より若宮執行委員長が連合愛媛副会長に、山内俊夫さんが執行委員に、谷口副執行委員長が女性枠代表として新たに執行委員に選出され、最後に木原会長の団結ガンバローで大会を締めくくった。



県市町振興課交渉(2011.11.16)
-
11月16日県庁にて、若宮執行委員長を始め13人の執行委員が集まり、県市町振興課と交渉を実施した。
始めに若宮執行委員長より、11月2日に出された人事委員会勧告は極めて厳しい勧告だった。また現給保障については、まだ多くの職員が現給保障を受けている。この世代は、子どもにお金がかかる世代なので、適切なアドバイス出すように求めた。
これに対し県市町振興課長は、公務員を取り巻く環境は年々厳しくなっている。公務員は、住民からの税金から成り立っているので、住民の理解が必要である。と回答した。
県市町振興課交渉では、重点課題を5項目に設定し交渉を行った。【主な要求】
(1) 2006年の給与構造改革における現給保障制度を廃止しないこと。
(2) 市町村合併に伴う旧自治体間の賃金格差の是正については、県が合併時に示した「再計算方式」に基づき早急に改善されるように指導すること。
(3) 県内の多くの市町自治体のラスパイレス指数は、全国平均を大きく下回っていることから早急な対応策を講ずるように助言すること。
(4) 1時間あたりの時間外勤務手当の単価算出については、労働基準法に基づいて給与条例を改正するよう指導すること。
(5) 男性職員の育児休業所得促進をすすめるとともに短期間所得者の期末手当の支給割合を改善すること。【回答】
(1) 高齢層の公務員賃金は民間よりも高く、定年延長制度導入のために是正していかなければならない。県人事委員会の勧告を踏まえ、各自治体に適正な判断をお願いしている。
(2) 市町村合併による職員間の賃金均衡をはかるべきだが、住民の理解が必要である。合併時の「再計算方式」は必ず実施しなければならないのではなく、各市町村間で判断するものである。
(3) 地方公務員の給与については、地公法24条に基づき条例によって定められている。ラスパイレス指数が低いからと言うだけでは、住民からの理解は得られない。
(4) 地方公務員は一部労働基準法に準じているので、労働基準法通り処理するのが必要である。
(5) 男性職員が育児に参加することは、必要であることから適切な助言をする方針である。



11月9日愛媛県市長会長交渉(2011.11.09)
-
11月9日15時から西予市庁舎にて、自治労県本部・都市評議会議長・西予市職労の10人で愛媛県市長会長三好幹二西予市長交渉を実施した。
市町村合併から約5年経過したが、合併自治体間の賃金調整や業務量の増加等に対する措置が行われていない自治体もあり、職員の士気や精神的な負担はピークに達しています。また、今年の人事院勧告では、2006年の給与構造改革時の現給保障制度を廃止するという勧告が行われました。高齢職員のモチベーションにも大きく影響する問題がある勧告と言わざるを得ません。今回は13項目の要求を書面でお願いしましたが、その中でも重要な以下5項目について強く交渉要求しました。【主な要求書】
【1】 市町村合併に伴う自治体職員間の賃金調整については、県市町振興課が示している「再計算方式」に基づいて、早急に改善を行うこと。
【2】2011年人事院勧告で行われた、2006年給与構造改革における現給保障制度を廃止しないこと。
【3】労働基準法に抵触している超過勤務手当の単価計算方法のを改善するとともに、中高年の賃金改善を図ること。人事院が勧告したような40~50歳台の職員の賃金引き下げを行わないこと。一時金の支給月数の改善を図るとともに、期末手当に一元化すること。あわせて、給与構造改革に伴う現給保障については制度導入時の趣旨に則り、堅持すること。
【4】人事院の意見の申し出を踏まえて、国と同時期に定年延長を開始することができるよう検討を開始すること。また、高齢者再任用制度の導入をはかり、希望者全員の再任用を行うこと。
【5】男性職員の育児休業取得促進をすすめるとともに短期間取得者の期末手当の支給割合を改善すること。今回、東日本大震災等で人事院勧告が遅れたことにより、交渉は行ったものの11月になってしまい県市長会の会合が10月に終了しており、意見としては聞いてもらえたが、「個別で市長にあたってもらわないと無理ですと返答された。」ただ、「要求書を市長会宛にいただいているので各市長へは文章で流しますと返答いただいた。」次回は、「市長会前の要求であれば会長として意見交換もできますと返答いただいた。」三好会長も「給与を下げることは反対、地域も冷え込んでしまうし人事委員勧告がなくなれば大変だと発言された。」
自治労県本部も次年度交渉は、市長会開催までに要求書を提出し交渉していきたい。
今後も県市町振興課交渉・県町村会長交渉を行い確定交渉に全力をあげていきますので、単組でもしっかり確定交渉してください。



人事委員会交渉状況(2011.10.21)
-
10月21日県庁にて、自治労県本部・県職労・愛媛教組の三者合同で県人事委員会交渉を実施した。勧告については、11月初旬になるとの見解を示した。
9月30日に人事院は国家公務員に対して2011勧告を行ったが、2006年の給与構造改革時の現給保障の廃止や本来上がるべき一時金の改定見送りを中心とした勧告であった。これは、労働基本権制約の代償機関としての人事院の役割を果たしているとは到底言い難く、勧告制度を人事院自らが否定したものであると言わざるを得ない。
当日の交渉では、県人事委員会が賃金改定作業を進めるにあたり自治体労働者の生活を守るという基本的な使命を認識し対応するよう強く要請した。
自治労県本部は、県人事委員会勧告の後、県市町振興課交渉・県市長会長交渉・県町村会長交渉を皮切りに、確定交渉に全力をあげる。主な交渉内容及び回答は下記のとおり。【主な要求書】
【1】 中高年の賃金改善を図ること。人事院が勧告したような40~50歳台の職員の賃金引き下げを行わないこと。一時金の支給月数の改善を図るとともに、期末手当に一元化すること。あわせて、給与構造改革に伴う現給保障については制度導入時の趣旨に則り、堅持すること。
【2】住居手当について、借家分の支給額の引き上げを行うこと。持ち家分については、取り組みによる愛媛県が独自に改善を図ってきたものであり、現行水準を維持すること。
【3】 男性職員の育児休業取得促進を進めるとともに、短期間取得者の期末手当の支給割合を改善すること。
等を中心に交渉を実施した。【回答】
【1】 今回の人事院勧告で出された賃金改定について、政府は勧告をしない方向のようであるが、全部を把握できていない状況。愛媛県では、詳細の数値は言えないが月例給においては人事院勧告を上回っている状況。一時金については、ほぼ国並みの数値が出ている。最終数値を分析し適正な勧告を行う。また、現給保障については、給与構造の見直しにより導入されたが、愛媛県は地域手当の対象外でもあり、国と異なることは承知している。しかし、国が現給保障の廃止を出した以上、何らかの形で触れなくてはいけないと考えている。
【2】 自宅の係る住居手当については報告に入れるかは検討中。基本的に、存続するか否かは任命権者に委ねている。
【3】 男性職員育児休業については国と同じような形で報告に入れたい。



第72回県本部定期大会(2011.10.8)
-
10月8日(土)エスポワール文教会館にて、2012年度第72回定期大会が開催された。
その前段として前日の7日(金)には、各部会評議会の大会が開催され2012年度の新たな執行部体制や運動方針を決定した。
第72回定期大会では、副執行委員長枠を従来の4人以内から組織拡大・強化担当2人、女性副執行委員長を加え7人以内とし、組織を強化していくことを確認した。
また、2013年には人事院勧告は廃止され労働協約締結権が付与されることから、自分たちの賃金・労働条件は労使交渉で決定していく自律的労使関係制度が予定されている。
これに対して県本部では対策委員会を設置し、現在公平委員会または県人事委員会に職員登録団体として承認を受けていない単組については、制度移行時に「認証労働組合」として自然移行する方向であることから職員登録団体としての手続きを進める。
全単組の規約や規約に関わる規則・規程をチェックし、改正が必要な場合は単組と協議を行っていく。
単組・県本部・本部間でしっかりと連携をとり、『要求-交渉-妥結-協定-協約化』のサイクルの確立に向け、全力をあげて取り組みを進める方針で第72回定期大会を閉会した。